「最近のスマホは高すぎるけど、結局どれを選べばいいの?」と迷っていませんか。
2026年のスマートフォンは、見た目以上に“中身”が大きく進化しています。AppleのA19 Pro、QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 2、SamsungのExynos 2600、そしてGoogleのTensor G6。各社が独自CPUコアや2nmプロセスを武器に、これまでとは次元の違う性能競争を繰り広げています。
Geekbenchではシングルコア約4,000点、マルチコア11,000点超といった数字も登場し、AI処理や120fpsゲーミングも当たり前の時代になりました。しかし、ベンチマークの数字だけでは「発熱しにくいのは?」「バッテリーが持つのは?」「長く快適に使えるのは?」といった疑問の答えは見えてきません。
この記事では、カスタムCPUコアの違い、2nmや裏面電源供給といった最新半導体技術、AI性能や実利用での体験差、日本市場の動向までをわかりやすく整理します。難しい専門用語もかみ砕いて解説しますので、ガジェットにそこまで詳しくない方でも安心して読み進められます。
読み終えるころには、2026年に「買って後悔しないスマホの選び方」がはっきり見えてくるはずです。
- 2026年はスマホCPUの戦国時代──何がそんなに変わったのか
- カスタムCPUコアとは?Arm標準コアとの違いをやさしく解説
- 2nmプロセスとGAAFETの衝撃──発熱と電池持ちはどう変わる?
- 裏面電源供給(BSPDN)がもたらす性能と安定性の進化
- Snapdragon 8 Elite Gen 2の実力──全コア高性能は本当に有利?
- Apple A19 Proの進化──6-wide Eコアが変えたiPhone体験
- Exynos 2600とTensor G6──SamsungとGoogleの独自戦略
- ベンチマークで比較:Geekbench・AI性能・ゲーム実測の違い
- 日本市場の動向と買い替えタイミング──2年返却時代の選び方
- 2026年に選ぶべきスマホは?用途別おすすめCPUタイプ
- 参考文献
2026年はスマホCPUの戦国時代──何がそんなに変わったのか
2026年のスマホ業界は、まさに「CPU戦国時代」と呼べる状況です。これまで長年にわたり、Armの標準設計をベースに各社が性能を競う構図が続いてきましたが、そのバランスが大きく崩れました。
いま起きているのは、単なる性能向上ではありません。設計思想そのものが変わり、各社がまったく異なる方向に進み始めたことが最大のポイントです。
背景にあるのは「完全カスタム化」と「超・垂直統合」です。Apple、Qualcomm、Armという巨大プレイヤーが、それぞれ独自路線を打ち出しています。
| 企業 | 2026年の方向性 | 特徴 |
|---|---|---|
| Apple | 完全自社設計の深化 | Eコアまで大幅強化、2nm先行採用 |
| Qualcomm | 独自カスタムコア化 | 全コア高性能「Oryon」 |
| Arm | 設計+物理最適化を一体提供 | Lumex CSS戦略 |
たとえばQualcommは、Nuvia買収を経て生まれた「Oryon」コアへ全面移行しました。従来のArm標準コアに依存せず、PC向け設計思想をモバイルに持ち込んだのです。Notebookcheckなどの分析によれば、マルチコア性能は1万点超えの水準に到達し、スマホがノートPC並みの処理能力を持つ時代に入りました。
一方Appleは、TSMCの2nmプロセスをいち早く採用し、効率コアまで強化。解析情報ではEコアが6命令同時デコードに達したとされ、もはや「省電力専用」という位置づけではありません。
さらにArm自身も、単なるIP提供企業から脱却を図っています。EE Timesが報じたように、CPUだけでなくGPUや物理設計までまとめた「Lumex CSS」を提供し、パートナーを強く囲い込む戦略へ転換しました。
しかも変化は設計だけではありません。TSMCやSamsungが量産段階に入れた2nm世代では、GAAFET構造が本格化。TSMCによれば、前世代比で同性能なら消費電力を25〜30%削減できるとされています。
つまり2026年は、「速くなった」だけではなく、作り方・競争のルール・電力効率の常識までが塗り替わった年なのです。これが“戦国時代”と呼ばれる理由です。
カスタムCPUコアとは?Arm標準コアとの違いをやさしく解説

スマートフォンの性能を左右する「CPUコア」には、大きく分けてArm標準コアとカスタムCPUコアの2種類があります。
どちらも同じArmアーキテクチャ(命令セット)を使っていますが、中身の作り方がまったく違います。
ここを理解すると、なぜメーカーごとに性能や電池持ちに差が出るのかが見えてきます。
| 項目 | Arm標準コア | カスタムCPUコア |
|---|---|---|
| 設計元 | Armが設計 | メーカーが独自設計 |
| 自由度 | 低い(基本設計は共通) | 高い(内部構造を自由に設計) |
| 代表例 | Cortex-C1 Ultra など | Apple Aシリーズ、Qualcomm Oryon |
| 差別化 | 難しい | 大きく可能 |
Arm標準コアは、いわば「完成済みの高性能エンジン」を購入して車に載せるイメージです。
設計や検証はArmが行っているため、開発期間を短縮でき、安定性も高いのが強みです。
EE Timesによれば、Armは近年「Lumex CSS」という形で物理設計データまでセット提供し、さらに導入しやすくしています。
一方でカスタムCPUコアは、「エンジンそのものを自社で設計する」方式です。
使えるのはArmの命令セット(ISA)だけで、内部のパイプライン構造やキャッシュ設計、分岐予測までゼロから作ります。
そのため開発コストは非常に高いですが、性能特性を自社製品に最適化できるのが最大の魅力です。
たとえばAppleはアーキテクチャライセンスを取得し、A19 Proで6-wideデコードの高性能Eコアを設計しています。
QualcommもNuvia買収後、「Oryon」という完全カスタムコアへ移行しました。
HWCoolingの解析によれば、OryonはPC向け設計をベースにした広いデコード幅を持つ点が特徴です。
つまり、どちらもArm系チップですが、標準コアは「共通ベース」、カスタムコアは「メーカー専用チューン」と考えるとわかりやすいです。
スマホの動作のキビキビ感やバッテリー持ち、AI処理の速さの差は、こうした設計思想の違いから生まれています。
最近のハイエンド機種で体感差が広がっている背景には、このカスタム化の波があるのです。
2nmプロセスとGAAFETの衝撃──発熱と電池持ちはどう変わる?
2nmプロセスの本質は、単に「数字が小さくなった」ことではありません。トランジスタ構造そのものが刷新され、スマホの発熱と電池持ちに直結する電力効率が大きく変わろうとしています。
その中心にあるのがGAAFET(Gate-All-Around FET)です。従来のFinFETは電流の通り道を3方向から囲む構造でしたが、GAAFETはチャネルを360度取り囲みます。これにより電流の漏れを抑えやすくなり、低い電圧でも安定動作しやすくなります。
TSMCの公式情報によれば、2nm世代(N2)は前世代3nm(N3P)比で、同じ消費電力なら10〜15%の性能向上、同性能なら25〜30%の消費電力削減が見込まれています。これはピーク性能だけでなく、日常利用の体感にも影響します。
| 比較項目 | 3nm世代 | 2nm世代(GAAFET) |
|---|---|---|
| トランジスタ構造 | FinFET | GAAFET(ナノシート) |
| 電流制御 | 3方向 | 360度 |
| 電力効率 | 基準 | 最大約25〜30%改善 |
では、これが実際のスマホ体験にどう効くのでしょうか。たとえば動画撮影や高負荷ゲームでは、SoCが高クロックで長時間動作します。電圧を下げても安定しやすいGAAFETなら、同じ処理でも発熱を抑えやすくなります。
発熱が減ると、端末はサーマルスロットリング(熱による性能制限)を起こしにくくなります。結果として、パフォーマンスが長時間安定しやすくなり、フレームレートの落ち込みも抑えられます。
さらに重要なのが待機時や軽作業時の効率です。リーク電流が少ないということは、画面オフ時やSNS閲覧といった低負荷シーンでの無駄な電力消費が減るということです。積み重なると、1日のバッテリー持ちに確実に差が出ます。
Samsungも2nm世代(SF2)でGAA構造を本格化させ、歩留まり改善を進めていると報じられています。製造安定性が高まれば、高性能と低発熱を両立するチップがより広く普及していきます。
つまり2nmとGAAFETの衝撃は、「ベンチマークが少し伸びる」という話ではありません。スマホが熱くなりにくく、電池が減りにくいという、誰でも体感できる変化こそが本当のインパクトです。
今後はピーク性能の数字以上に、ワットあたり性能と持続性能が重視される時代になります。2nm世代は、その流れを決定づける大きな転換点になりそうです。
裏面電源供給(BSPDN)がもたらす性能と安定性の進化
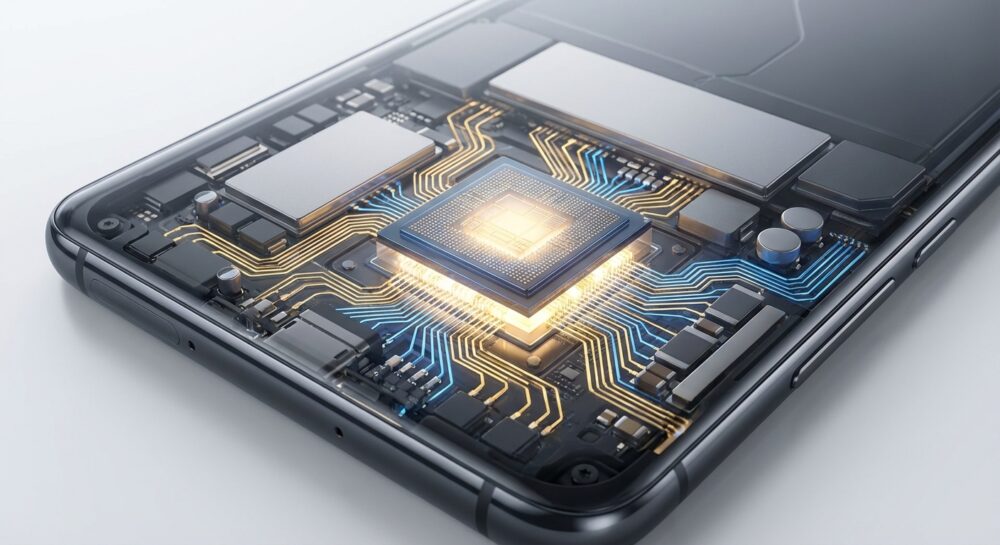
スマートフォンの性能を語るうえで、2026年以降の大きな転換点になるのが裏面電源供給(BSPDN)です。これはチップの“電気の通り道”を根本から見直す技術で、処理性能だけでなく安定性にも直結する進化です。
これまでの半導体では、トランジスタの上に信号線と電源線が混在していました。しかし微細化が進むにつれ、配線の抵抗増加による電圧低下、いわゆるIRドロップが深刻化していました。高負荷時にクロックが安定しない原因の一つです。
BSPDNは電源配線をチップの裏側に分離することで、このボトルネックを解消します。電源をより太く低抵抗な経路で直接供給できるため、CPUやGPUが高い周波数を維持しやすくなります。
| 項目 | 従来構造 | BSPDN採用時 |
|---|---|---|
| 電源配線 | 表面に信号と混在 | 裏面に専用層を配置 |
| 電圧安定性 | 高負荷時に低下しやすい | 高負荷でも安定 |
| 配線自由度 | 混雑しやすい | 信号線を最適配置可能 |
TSMCが発表しているA16世代プロセスでは、この裏面電源供給を本格導入する計画が示されています。Tom’s Hardwareの報道によれば、電源供給効率の改善によりパフォーマンスと電力効率の両立が可能になるとされています。
ライトユーザーにとって重要なのは体感です。例えば高負荷なゲームや動画編集時にフレームレートが急に落ちる、発熱でパフォーマンスが下がる、といった現象の抑制が期待できます。
電圧が安定するということは、ピーク性能だけでなく「持続性能」が向上するということです。ベンチマークの瞬間的な数字よりも、長時間使ったときの快適さに直結します。
さらに、表面の配線層が信号専用になることで回路配置の自由度が高まり、ロジック密度向上にも寄与します。これはチップ面積の縮小やキャッシュ増量につながり、結果としてアプリの読み込み速度やAI処理の応答性改善に波及します。
半導体専門メディアSemiWikiでも指摘されている通り、微細化が限界に近づく中で配線技術の革新は不可欠とされています。BSPDNは単なる小改良ではなく、設計思想そのものを変えるアプローチです。
今後のフラッグシップスマートフォンでは、2nm世代と組み合わさることで、より高クロック・低消費電力・高安定性という三拍子が実現していきます。見えない部分の進化ですが、日常の操作感を底上げする重要なテクノロジーです。
派手なコア数やGHzの数字に目が行きがちですが、電気をどう届けるかという基礎設計の進化こそが、次世代スマートフォンの体験品質を支える土台になっています。
Snapdragon 8 Elite Gen 2の実力──全コア高性能は本当に有利?
Snapdragon 8 Elite Gen 2の最大の特徴は、いわゆる「全コア高性能(All Big Core)」設計を本格的に採用している点です。従来のスマホ向けCPUは「高性能コア+高効率コア」という役割分担が一般的でしたが、このチップは考え方がまったく異なります。
搭載されるのは、最大4.47GHzで動作するOryon Primeコア2基と、3.53GHzのOryon Performanceコア6基という2+6構成です。低電力専用のEコアは存在しません。
| 項目 | Snapdragon 8 Elite Gen 2 |
|---|---|
| CPU構成 | Oryon Prime×2 + Performance×6 |
| 最大クロック | 最大4.47GHz |
| 効率コア | 非搭載(全コア高性能) |
Qualcommの説明によれば、「高性能コアを低電圧・低クロックで使い、処理を一瞬で終わらせてスリープに戻す“Race to Sleep”」のほうが、結果的に電力効率が良いとしています。Product Briefでも同様の思想が示されており、設計段階から“常に余裕のある性能”を前提にしていることがわかります。
実際、Geekbench 6ではマルチコアで11,000点超というスコアが報告されています。これは複数の高性能コアを同時にフル活用できる動画書き出しやゲーム配信、AI処理などで特に強みを発揮します。
ではライトユーザーにとって有利なのでしょうか。ポイントは「体感の安定性」です。
SNSを見ながら音楽を再生し、バックグラウンドで写真をクラウド同期するといった日常的なマルチタスクでも、すべてのコアが高性能なため処理待ちが起こりにくいです。アプリの切り替え時にも引っかかりが少なく、余裕のある動作が続きます。
一方で、常時重い処理をするわけではない使い方では、従来型との違いが劇的に感じられるとは限りません。重要なのはピーク性能よりも、発熱と持続性能のバランスです。
OryonはもともとPC向け設計をルーツに持ち、広い命令デコード幅や大容量キャッシュを備えています。これにより複雑化したWebページやAI処理でも処理効率が高く、PCとスマホの境界を縮める方向に進化しています。
結論として、Snapdragon 8 Elite Gen 2の強みはベンチマークの数字そのものよりも、どんなアプリでも“余力を残して動く”安心感にあります。ライトユーザーでも、数年先まで快適に使い続けたい人にとっては、この設計は確かに有利と言えます。
Apple A19 Proの進化──6-wide Eコアが変えたiPhone体験
iPhone 17 Proに搭載されるA19 Proは、単なる性能向上にとどまらない進化を遂げています。特に注目すべきは、高効率コア、いわゆるEコアの“怪物化”です。これまでEコアは省電力担当という脇役的な存在でしたが、A19 Proではその常識が大きく変わりました。
解析情報によれば、A19 ProのEコアは6-wide decode(6命令同時デコード)という非常に広いフロントエンドを備えています。これは一部の他社製Pコアに匹敵する規模です。命令を一度に多く読み取れるため、軽い処理だけでなく“中くらいの重さ”の作業も余裕でこなせるようになりました。
| 項目 | A19 Pro Eコア | 従来の一般的Eコア |
|---|---|---|
| デコード幅 | 6-wide | 2〜4-wide程度 |
| 主な役割 | 中負荷まで広範囲に対応 | 軽負荷中心 |
| Pコア起動頻度 | 大幅に低減 | 中負荷で起動しがち |
この進化が体験にどう影響するのでしょうか。たとえばSNSのスクロール、Safariでの複数タブ閲覧、写真アプリでの軽い編集といった日常操作です。これらの処理の多くをPコアを起動せずEコアだけで完結できるようになっています。
結果として、発熱が抑えられ、バッテリー消費も穏やかになります。実際、海外メディアの解析ではEコアが前世代比で最大約29%向上しながら消費電力はほぼ据え置きと報告されています。ライトユーザーほど、この恩恵を強く感じやすいでしょう。
さらに、AppleはPコア側のROB(Reorder Buffer)も拡張しています。命令を効率よく並べ替えて同時実行する能力が高まり、Geekbench 6のシングルコアスコアは約4,000点に迫る水準とされています。ベンチマークの数字以上に、アプリの起動や画面遷移の“間”がさらに短くなっている点が重要です。
半導体製造面では、TSMCの2nmプロセス(N2)をいち早く採用したことも大きな要素です。TSMCの公式説明によれば、同世代比で消費電力を20%以上削減可能とされており、その余裕をキャッシュ増量などに振り向けています。A19 Proではシステムレベルキャッシュが32MBに拡大したとの情報もあります。
高性能を“必要なときだけ”ではなく、“常に効率よく”出せる構造こそがA19 Proの本質です。Eコアが進化したことで、普段使いのほとんどが静かで滑らかになり、バッテリー持ちも安定します。スペック表には現れにくい部分ですが、毎日触れるたびに違いを実感できる進化といえます。
Exynos 2600とTensor G6──SamsungとGoogleの独自戦略
ハイエンドSoCの主役がQualcommやAppleである一方で、SamsungとGoogleも“自分たちらしさ”を前面に出した戦略を進めています。その象徴がExynos 2600とTensor G6です。
両社に共通するのは、単なる性能競争ではなく、自社エコシステムに最適化したチップ作りへと舵を切っている点です。
Exynos 2600とTensor G6の方向性
| 項目 | Exynos 2600 | Tensor G6 |
|---|---|---|
| 製造プロセス | Samsung 2nm(SF2) | TSMC 2nm世代(報道ベース) |
| CPU構成 | Arm最新C1 Ultra系を高クロック化 | Arm系+Google最適化 |
| 強み | AMD RDNA系GPU | TPUによるAI処理 |
まずExynos 2600は、Samsungファウンドリの2nm GAAプロセス「SF2」を採用するフラッグシップです。Samsung Semiconductorの公開情報によれば、同世代は電力効率とトランジスタ密度の向上が大きな柱とされています。
さらに注目は、AMDのRDNAアーキテクチャをベースにしたXclipse GPUです。海外メディアの報道では、BasemarkのレイトレーシングテストでSnapdragon系を上回ったとの結果も伝えられています。
つまりExynos 2600は、「製造技術+グラフィックス性能」で存在感を示す戦略といえます。
一方のTensor G6は、方向性がまったく異なります。これまでSamsung製造だったTensorを、TSMCへ切り替えるという大きな転換が報じられています。
背景には、Pixelユーザーから長年指摘されてきた発熱やバッテリー持ちへの不満があります。Android Authorityや9to5Googleによれば、GoogleはTensor G6でピーク性能よりも電力効率を重視しているとされています。
Googleが本当に強化したいのはCPUやGPUの絶対性能ではなく、TPUを活かしたオンデバイスAI体験です。
たとえばリアルタイム文字起こしや画像編集、Gemini Nanoのローカル処理などは、クラウドに頼らずスマホ単体で完結する設計思想です。これは「スペック表の数字」では測りにくい価値です。
Samsungが垂直統合による主導権回復を狙うのに対し、GoogleはAI体験を軸に差別化を図る。どちらもQualcomm依存からの“自立”という点では共通しています。
Exynos 2600とTensor G6は、単なる新型チップではありません。Android陣営の多様化を象徴する存在として、2026年のスマートフォン市場に大きな意味を持つのです。
ベンチマークで比較:Geekbench・AI性能・ゲーム実測の違い
ベンチマークの数字は一見わかりやすいですが、実際の体感とは必ずしも一致しません。Geekbench、AI性能、ゲーム実測はそれぞれ測っているものが違うため、読み解き方を知ることが重要です。
まずは代表的なスコアの傾向を整理します。
| 項目 | 強みを見せる傾向 | 体感への影響 |
|---|---|---|
| Geekbench シングル | A19 Pro 約4,000点 | アプリ起動・Web表示の速さ |
| Geekbench マルチ | 8 Elite Gen 2 11,000点超 | 動画書き出し・重い同時処理 |
| AI推論 | 各社ほぼ拮抗 | 生成AI・画像処理の待ち時間 |
Geekbench 6では、リーク情報によればA19 Proがシングルコア約4,000点と依然トップクラスです。これはIPCとクロック効率の高さを示しており、WebブラウジングやSNSのスクロールといった日常操作での「キビキビ感」に直結します。
一方、Snapdragon 8 Elite Gen 2はマルチコアで11,000点を超えるスコアが報告されています。Notebookcheckなどの検証でも触れられている通り、全コア高性能構成が効いており、動画編集やバックグラウンド処理では数値上有利です。
ただし重要なのは、Geekbenchは“瞬間的な最大性能”を測るテストだという点です。長時間使ったときの発熱や電力制御までは評価しきれません。
AI性能も同様です。各社ともNPUのTOPS値を強調しますが、実際にはINT4やINT8など混合精度での実効性能がカギになります。ArmのSME対応CPUやQualcommのHexagon、AppleのNeural Engineはそれぞれ最適化の方向性が異なり、単純な数値比較は難しい状況です。
そして体感差がもっともわかりやすいのがゲーム実測です。「原神」などの高負荷タイトルで120fpsにどれだけ張り付けるかが指標になります。iPhone 17 ProやSnapdragon 8 Elite搭載機では平均110fps以上を維持したというテスト報告もあり、消費電力は4〜5W台に収まるケースもあります。
ここで見ておきたいのは平均fpsと消費電力のバランスです。最大fpsが高くても、数分後にフレームレートが落ちるようでは快適とは言えません。
また、Exynos 2600はBasemarkのレイトレーシングテストでSnapdragonを上回ったとの報告もあります。これは特定条件下でのGPU性能の強さを示しますが、対応ゲームが限られるため、ライトユーザーには大きな差として感じにくい場合もあります。
結論として、Geekbenchは日常操作の軽快さ、AIスコアは生成機能の待ち時間、ゲーム実測は持続性能を見る指標です。数字の大小よりも「自分が何をよく使うか」で見ることが、後悔しない選び方につながります。
日本市場の動向と買い替えタイミング──2年返却時代の選び方
日本のスマートフォン市場は、いま大きな転換点にあります。世界的には性能競争や半導体の進化が注目されがちですが、日本ではそれ以上に「買い方」が選び方を左右しています。
特に影響が大きいのが、キャリア各社が提供する2年後返却型の端末購入プログラムです。端末を分割で購入し、24カ月後に返却すれば残価の支払いが免除される仕組みが主流になっています。
Counterpoint Researchによれば、2026年はこの2年返却サイクルが本格的に重なり、買い替え需要が強まる年になると分析されています。
| 購入年 | 主なモデル | 2026年の状況 |
|---|---|---|
| 2024年 | iPhone 15 / Pixel 8世代 | 返却・機種変更のタイミング |
| 2025年 | iPhone 16 / Pixel 9世代 | まだ支払い途中が中心 |
この構造の特徴は、「壊れるまで使う」よりも2年での計画的な更新が前提になっている点です。そのため日本では、4〜5年先を見据えたスペックよりも、「2年間快適に使えるかどうか」が重視されやすい傾向があります。
たとえば2024年モデルからの買い替えでは、処理性能の伸び以上に、オンデバイスAI機能やバッテリー持ちの改善が判断材料になります。GoogleがTensor G6で電力効率と発熱改善を重視しているのも、こうした市場特性を意識した動きといえます。
一方で、2nmプロセス採用モデルは部材コストの上昇が価格に反映されやすく、月額負担が増える可能性もあります。円安の影響も重なり、ハイエンドはさらに高額帯にシフトしています。
具体的には、次の3つが重要です。第一に発熱と電池持ち。日常利用で安定しているかどうかが満足度を左右します。第二にAI機能の実用性。翻訳、写真補正、要約などが生活に溶け込むかが鍵です。第三に下取り・残価設定の条件。実質負担額で比較する視点が欠かせません。
MM総研などの調査でも、日本ではiPhoneのシェアが依然高水準にある一方、Pixelが着実に存在感を高めているとされています。価格と体験のバランスが、これまで以上にシビアに見られている証拠です。
2026年は、単なる性能競争の年ではありません。2年後にどう感じているかを想像して選ぶことが、日本市場で後悔しないスマホ選びの新しい基準になっています。
2026年に選ぶべきスマホは?用途別おすすめCPUタイプ
2026年のスマホ選びで迷ったら、まず注目すべきはCPUの「設計思想」です。いまは単純なクロック数よりも、どんな用途に最適化されたコアなのかが体験を大きく左右します。
代表的なタイプを整理すると、次のように分かれます。
| CPUタイプ | 代表例 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 完全カスタム高性能型 | Oryon Gen 2 | 動画編集・重いゲーム |
| 高効率進化型 | A19 Pro | 日常操作・長時間利用 |
| AI特化バランス型 | Tensor G6系 | 写真編集・AI機能重視 |
| Arm最新標準型 | Cortex-C1 Ultra系 | 総合力重視 |
まず、ゲームや動画編集を本気で楽しみたい人には、QualcommのOryon Gen 2のような「全コア高性能型」がおすすめです。Notebookcheckなどのベンチマーク情報によれば、マルチコア性能は11,000点超クラスに達しており、複数アプリを同時に動かす場面でも余裕があります。
一方で、SNSや動画視聴、ネット検索が中心なら、AppleのA19 Proのような高効率コアが強化されたタイプが快適です。解析情報ではEコアでも6命令同時デコードという高性能設計が採用されており、日常操作のほとんどを低消費電力で処理できます。結果としてバッテリー持ちにも直結します。
写真編集やリアルタイム翻訳などAI機能を多用するなら、Tensor G6系のようなAI処理に重点を置いた設計が向いています。Googleは電力効率と発熱対策を重視するとしており、従来Pixelで課題とされたバッテリーや熱の改善が期待されています。
また、ArmのCortex-C1 Ultra系を採用する最新チップは、SME2といった行列演算拡張により、CPU単体でもAI処理をこなせるのが特徴です。Armの公式情報によれば、低遅延AI処理に強く、アプリ互換性の面でも安心感があります。
ライトユーザーであれば、必ずしも最上位のスコアは必要ありません。むしろ発熱が少なく、安定して長く使えるCPUを選ぶことが、2年間の満足度を左右します。
CPUタイプを理解して選ぶだけで、同じ価格帯でも体験は大きく変わります。スペック表の数字だけでなく、その裏にある設計思想に目を向けることが、2026年の賢いスマホ選びにつながります。
参考文献
- Arm:Software Licensing vs. IP Licensing
- EE Times:Arm Goes for Rebrand for Mobile CSS, Drops Cortex, Immortalis
- TSMC:2nm Technology
- SemiWiki:TSMC N2 Process Technology Wiki
- Qualcomm:Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform – Product Brief
- Arm:Arm C1-Ultra CPU | Flagship Performance for Client 2025 SoCs
- Counterpoint Research:Japan Smartphone Market: Replacement Demand May Strengthen in 2026 as “Two-Year Return” Program Reaches Maturity
- Wccftech:Samsung’s Exynos 2600 Chip Takes First Place On The Basemark Ray Tracing Leaderboard After Beating Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Android Authority:Google Pixel 11’s Tensor G6 might be a downgrade, but could also fix some big Pixel phone flaws
