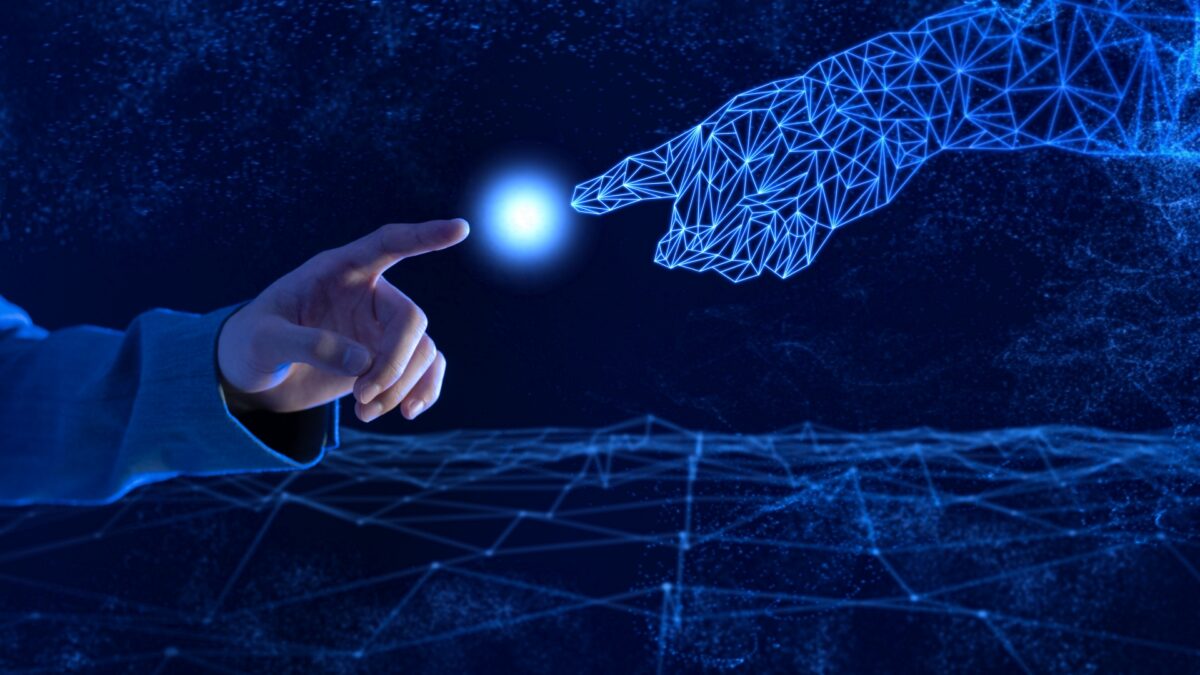Microsoftが次期Windows 11に導入を予定している「Windows Intelligence」は、ユーザー体験の向上を図る新機能として注目されている。Xのインサイダー、Albacoreによると、Windows Intelligence専用の設定ページが開発されており、プライバシーとセキュリティ設定の一部に配置される見通しだ。
このページでは、システム全体とユーザーごとにWindows Intelligence(WI)機能のオンオフが可能になり、WIリソースの使用履歴を閲覧できる。また、Appleの「Intelligence」に着想を得た可能性が指摘され、Copilot、Recall、ChatGPT、Live CaptionsといったWindows 11内のAI関連機能を統合するハブとして機能することが期待される。
Microsoftが先に公開予定のRecallはAIの個人向け機能として物議を醸しているが、Windows Intelligenceの登場により、その利便性と安全性が改めて問われることになるだろう。
Windows Intelligenceの設定ページがもたらす新たな可能性とは

Windows 11において導入される予定の「Windows Intelligence(WI)」専用の設定ページは、従来の設定と一線を画す内容となる見込みである。Albacore氏がX(旧Twitter)で発表した内容によれば、この設定ページでは、システム全体やユーザーごとのWI機能のオンオフを切り替えられるだけでなく、WIリソースを利用した直近のアクティビティも確認できるようになるという。
このように各ユーザーの設定を詳細に管理できるインターフェースが提供されることで、プライバシーやセキュリティの観点からも利便性が高まると考えられる。
Microsoftはこの設定ページの導入により、個別機能の管理と共に、ユーザーごとの最適化も目指している可能性がある。現在、Windows 11ではCopilotやRecallなどのAI機能が存在するが、それぞれが個別のページで設定されている。
この新しいページの登場によって、AI機能の一元管理が可能になれば、ユーザーは煩雑な設定操作から解放され、よりシームレスに利用できる環境が整うことが期待される。Microsoftがユーザーエクスペリエンスの向上を図るために新たな道を模索している証ともいえるだろう。
Recallとの違いと懸念されるプライバシーの課題
Windows Intelligenceの設定ページと既存のRecallとの関係は、Microsoftが強調する通り明確に区別される予定である。Recallは個人のローカル環境で機能するAIであり、一定のプライバシーリスクが取り沙汰されている。以前、MicrosoftはRecallに対する「スパイウェア的」との批判を受け、削除可能な仕様とするなど、ユーザーの懸念に対応してきた。
Windows Intelligenceも個人データの扱いに慎重であることが望まれるが、複数のAIリソースを一元管理する中で、情報の扱いがどのように改善されるかが注目される。
一方で、Albacore氏が示唆するように、Windows Intelligenceは単にアクティビティを管理するだけでなく、データの使用履歴をユーザーに明示することで、透明性を高めようとしていると考えられる。
これは、MicrosoftがAI機能に対して透明性と信頼性を確保しようとする取り組みの一環ともいえる。もし適切な管理がなされなければ、プライバシーに対する懸念が再燃する可能性もあるため、ユーザーが安心して利用できる運用方法が今後の課題となるだろう。
AppleのIntelligenceを参考にした可能性とその影響
Windows Intelligenceという名称や機能性は、Appleが展開する「Intelligence」の影響を受けた可能性がある。AppleのIntelligenceは、iPhoneやiPadで個人の行動を基にしたレコメンデーションや自動補完機能などを提供している。
Microsoftも同様に、Windows Intelligenceを通じてCopilotやRecall、ChatGPT、Live CaptionsといったAI関連機能を統合し、ユーザーの利便性向上を目指す意図があるように見受けられる。
Microsoftがこれまで注力してきたのは、AIとユーザーインターフェースの親和性であり、直感的で分かりやすい体験を提供することにある。これにより、WindowsユーザーもAppleユーザーと同様に、よりスマートな操作性を享受できる可能性が高まっている。
Albacore氏による情報が正確であれば、MicrosoftはAppleとの差別化を図りつつも、ユーザーに寄り添ったAI体験を提供することで、今後の競争において有利な立場を築こうとしているのかもしれない。