Googleが手掛ける最新のスマートウォッチ、Pixel Watch 3が登場した。フィットネス機能やバッテリー寿命の向上に加え、WearOS 5.0を搭載し、多くのアップデートが施されている。
一方で、デザインの重さやアプリ管理の煩雑さといった懸念も存在する。このデバイスは果たして、次世代スマートウォッチとしての期待に応えられるだろうか。
圧倒的なパフォーマンスとディスプレイの進化
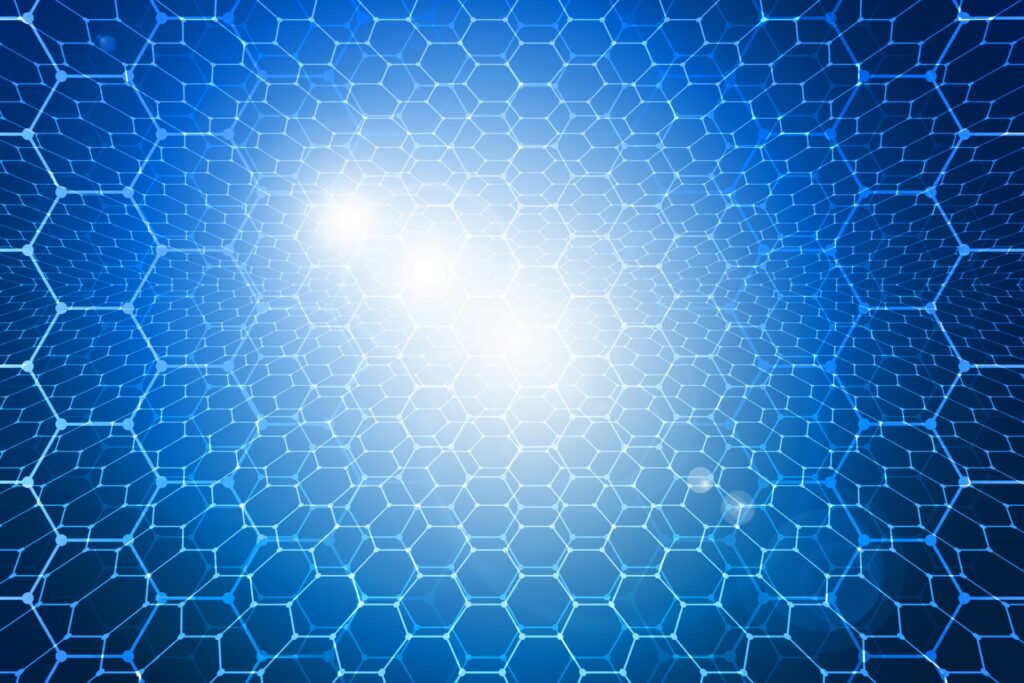
Google Pixel Watch 3は、Snapdragon W5 Gen 1チップとLTPOディスプレイを搭載し、これまでのスマートウォッチとは一線を画す性能を実現している。WearOS 5.0を採用し、操作性はさらに向上。スムーズなスクロールや、デジタルクラウンからの心地よいハプティックフィードバックが、ユーザーの体験を高める。また、デフォルトではGoogle製のアプリのみが搭載されているが、Play StoreからはWhatsAppやゲームなどサードパーティ製アプリもダウンロード可能である。
ディスプレイは「Actua Display」と呼ばれるAMOLEDを採用し、解像度は456×456ピクセル。最大2,000ニットの明るさで、屋外でも視認性は非常に高い。ベゼルが細くなったことで、従来モデルよりも画面が広く見える点も大きな進化である。しかし、ディスプレイの耐久性にはやや懸念が残る。Corning社のGorilla Glass 5が使用されているが、最新のガラス技術ではないため、落下時の破損リスクが考えられる。また、防塵・防水性能はIP68に対応しているが、水泳などの長時間の水中使用には注意が必要である。
健康管理の新機能とバッテリー寿命の向上
Pixel Watch 3は、GoogleのFitbitとの連携により、ヘルスケア機能が大幅に強化されている。フィットネス追跡では、従来プレミアム機能であった「デイリーレディネススコア」や「ターゲット負荷」などが無料で提供されるようになり、AIを活用した詳細なアクティビティ評価が可能である。また、初めて利用するユーザーには6ヶ月間のFitbitプレミアムが無料で提供され、個別のフィットネスルーチンも提案される。
さらに、Pixel Watch 3は心拍数、ストレスレベル、睡眠時のSpO2、体温、呼吸率などをリアルタイムで測定し、Fitbitアプリを通じて詳細なデータを確認できる。特に心拍数のモニタリングは高精度で、運動中や休息時の状態を的確に把握できる点が評価されている。バッテリーに関しては、45mmモデルであれば常時オンのディスプレイ(AOD)を有効にしても1日以上持続する。省エネモードや自動睡眠モードを活用すれば、2日以上の使用も可能であり、スマートウォッチとしては非常に優れたバッテリー性能を誇る。
使い勝手を損なうデザインの重量感
Pixel Watch 3は、外観デザインにおいても進化を遂げている。特に45mmモデルは、画面が広く見やすさが向上している一方で、その大きさが一部のユーザーには「重い」と感じられる可能性がある。特に、最初は腕に装着した際に、その重量感が気になることがある。しかし、しばらく使用することで次第に慣れ、睡眠中でも違和感なく使用できるとの評価もある。
本体にはリサイクルアルミニウムが使用されており、Googleのサステナビリティ目標に貢献している。また、円形の3Dガラスダイヤルは、クラシックなデザインを好むユーザーには好評だが、ガラス製の裏面は長時間使用時に手首に不快感を与えることがある。とはいえ、予算を重視するユーザーにとっては41mmモデルも選択肢として十分であり、45mmモデルのような高級感はないが、使い勝手は良好である。デザインの好みや装着感に個人差があるため、事前に実際に試着することが推奨される。
アプリ管理の複雑さがユーザー体験を阻害
Pixel Watch 3には、スマートウォッチとして多くの機能が搭載されているが、これらをフルに活用するためには複数のアプリを使い分ける必要がある。この点が、ユーザー体験をやや複雑にしている。例えば、時計の基本的な設定や管理には「Pixel Watch」アプリを使用するが、健康管理機能の多くは「Fitbit」アプリに依存している。さらに、Google Fitを利用することで追加のヘルスデータを取得できるため、3つのアプリを使い分ける必要が生じる。
このようなアプリ管理の煩雑さは、初めてスマートウォッチを使用するユーザーにとっては戸惑いを感じる要因となり得る。Googleがこれらの機能を一つのアプリに統合すれば、操作性が大幅に向上する可能性が高い。特に、AIを活用した機能の一部はデフォルトで無効になっているため、これらを有効にするためにはアプリ内での設定が必要である。Pixel Watch 3は、その豊富な機能が魅力である一方で、これらを効果的に管理するためのユーザー体験には改善の余地が残されている。
